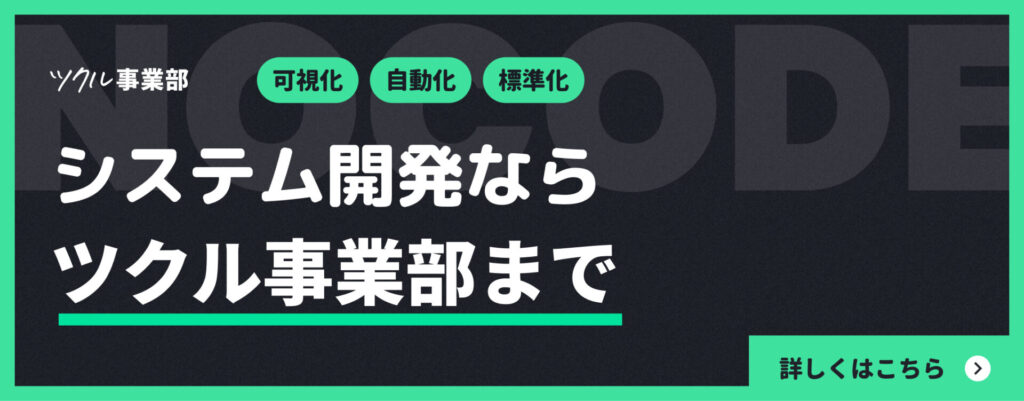新規事業企画書は、アイデアを事業化するまでの工程を説明し、新規事業のビジョンを示すために作成します。
特に投資家やパートナーなど、会社内外の関係者を惹きつけるために不可欠です。また、戦略や収支計画を詳しく立案することで、成功する確率を高められるという効果もあります。
しかし、実際に新規事業企画書を書いたことがある方は多くないでしょう。書き方、抑えるべき内容、書き方のポイントなど、わからないかもしれません。
そこでこの記事では、新規事業企画書の概要や、書くべき内容をご説明します。そして、テンプレートを活用した新規事業企画書の書き方も解説します。
皆さんのビジネスアイデアの実現の参考となれば幸いです。
\開発実績多数!システム開発のプロ集団/
新規事業企画書とは
新規事業企画書とは、名前の通り、これから行う新規事業についてまとめた資料です。ビジネスアイデアを事業にするための設計図ともいえます。
新規事業企画書には、以下のような項目が盛り込まれます。
- 事業の内容
- 事業を行う理由
- 商品やサービスの説明
- 市場分析とマーケティング戦略
- 利益を出す方法
- 予算と資金調達計画
- 収支計画
- 裏付けとなるデータ
ビジネスアイデアを具体的にイメージできるようにし、新規事業の方向性や戦略を明確に示すのです。
新規事業企画書を作成する目的
新規事業企画書の作成には、主に2つの目的があります。
1つ目の目的は、新規事業の計画を他人に明確に説明して伝えることです。
社内で自分が中心となり新しい事業を推進したいならば、経営層の承認を得る必要があります。起業するならば、出資や融資を得るために外部に事業を説明しなければなりません。また、新規事業に関わるチーム内やパートナーと、ビジョンを共有するためにも事業内容の説明が必要です。
もう1つの目的は、新規事業の計画書とすることです。
新規事業企画書に計画をまとめることで、成功見込みがあるか判断しやすくなります。そして、実際に新規事業を開始した後には、計画通り進んでいるか、進捗を測る指標にもなります。
既存事業企画書との違い
既存事業企画書も、新しい企画を説明し、社内での承認を得ることを目的に作成されることがほとんどです。つまり、目的は新規事業企画書と大きく変わりません。
しかし、既存事業企画書は、すでに行われている事業分野に関するものです。そのため、既存の事業から得られた実績をもとに作成されます。企画を説明する根拠には、経験や実際に得られた数値が使われます。
例えば、以下のような項目です。
- 既存事業の現状
- 業績と成果
- 財務状況
これらの実績を土台として、以下のような新しい企画が策定されます。
- 成長戦略や拡大計画
- 競合対策
- ブランディング
既存事業企画書では、過去のデータと今後の持続性が重視されるのです。
新規事業企画書を作成するメリット
新規事業企画書を作成することで、多くのメリットが得られます。ここでは主な3つのメリットを説明します。
事業を客観視できる
新規事業企画書を作成するには、新しいビジネスアイデアを整理し、他の人に伝えるためにまとめることが必要です。その過程で、ビジネスアイデアを客観視できます。
事業化できる良いアイデアが思い浮かぶと、嬉しくなり、興奮してしまうこともあるでしょう。しかし、新規事業企画書を作成するためには、アイデアを細部まで検証する必要があります。核となるアイデアの部分が優れていても、それだけでは多くの人を説得できません。
新規事業企画書を作成することで、客観的に見ても整合性の取れた形にまとめられるのです。ビジネスモデルだけでなく、ビジョンや計画も明確にでき、多くの関係者と共有できます。
検討すべきポイントが明確になる
新規事業企画書を作成するためには、ビジネスアイデアを客観視する必要があります。その際に、新規事業案に足りていない点が見えてきます。検討すべきこと、検討できていないこと、埋めなければならないポイントが明確になるのです。
特に新規事業では、自社や自分がノウハウを持っていない部分もあります。また、十分に市場が確立されていない場合もあるでしょう。そのため、新規事業企画書を作成することで判明する、更なる検討や市場調査が必要なポイントも重要です。
それにより、新規事業に投資すべきか、どのようなポイントをさらに検討すれば投資の判断ができるのかが明確になります。
スムーズに承認・決裁を得られる
新規事業企画書には、新しいビジネスの立ち上げから成長までの計画が書かれます。成功のための道筋と、なぜ成功できるかの理由も盛り込まれています。つまり、新規事業のアイデアを聞いた人が思い浮かぶ疑問への答えと、その根拠となるデータが示されているのです。
そのため、ビジネスアイデアを論理的に説明し、不明点やリスクについても先回りして提示できるのです。社内の経営層、社外の金融機関や取引先などに対して、ビジネスの方向性や戦略を明確にすることで、スムーズに承認や決裁を得ることができます。
新規事業企画書の書き方
ここからは新規事業企画書の具体的な書き方を説明します。主要な項目や、書くべき内容に分けて解説しますので、全体像をつかんでください。
表紙・目次
新規事業企画書を渡された人が最初に見るのは表紙です。興味を持ってもらい、読み進んでもらえるものにする必要があります。
表紙には、新規事業の内容や特徴を端的に示すタイトルを表記しましょう。ただ「新規事業企画書」と書いてあるだけでは、どのような事業かわからず、見る人が興味を持てません。逆に長すぎても、面倒でつまらなそうな印象を与えてしまいます。
また、タイトルと共にキャッチコピーやロゴなどを入れ、読み手の目を引くのも効果的です。
そして、表紙の次のページには目次を入れ、新規事業企画書の全体像がわかるようにします。
会社概要
新規事業の企画は、社外の関係者にも説明する機会が多いものです。そのため、会社概要を記載することが多くなっています。
すでに他の事業も行っている会社であれば、会社名や設立年月日と沿革、既存事業内容、規模や売上の推移などを記載します。経営状態の安定した企業であることを示し、信頼を得られるように心がけましょう。
新規事業を行うために設立した会社や起業後間もない会社の場合、メンバーとその経歴やスキルを中心に記載するのが一般的です。新規事業を行うのに適切なメンバーで、成功できることをアピールしましょう。
解決したい課題
解決したい課題とは、自社が利益を上げるために解決する課題ではありません。社会が抱えている課題を指します。その課題を新規事業でどのように解決するのか提示します。
例えば、以下のようなものです。
- 収穫したミカンを加工する際に捨てられている皮を材料に入浴剤を作ることで、無駄をなくし新しい価値をうむ。
- 在宅ワーク中心の人材紹介サービスを立ち上げ、働きたいが出社が難しいママに仕事を、人材不足の企業にスキルを持った人材をもたらす。
- タンスの肥やしになっている服を二次流通させ、埋もれていた価値を社会に還元する。
これから行う新規事業が社会的な意義を持ち、その成功により社会をより良くできることを示すのです。新規事業によって利益を得るだけでなく、自社の価値を上げられることを説明します。
それにより、経営層やステークホルダーに新規事業を印象付け、承認を得やすくなる効果も狙えます。
自社の課題
自社の課題では、自社が新規事業を行うべき理由を説明します。
まず、ほとんどの企業は利益を増やすことが課題です。そのため、新規事業で利益を出すことが課題を解決する方法となります。
また、既存の事業によって得たノウハウや、社内の人材を有効活用することも課題の一つです。既存の事業領域が伸び悩んでいる、または市場が縮小している場合には、さらに重要です。
会社のリソースは限られています。その中でリスクのある新規事業を開始するには、十分な理由や成功見込みが必要です。そのため、自社の課題を示し、それを新規事業が解決できることを納得してもらう必要があるのです。
新規事業の概要
新規事業企画書を読む人たちに、どのような事業なのかをイメージしてもらうための項目です。
説明すべきことは、例えば以下のようなものです。
- ビジネスのコンセプト
- 目標やビジョン
- 提供するサービスや商品とその価値
- ターゲットとなる市場
事業を具体的に理解してもらうとともに、魅力的に伝えられるように説明しましょう。
ビジネスモデル
ビジネスモデルとは、新規事業での利益の上げ方です。誰に、どのような価値を、どのように提供するのか。それによって、誰から、どのような対価を受け取るのか。ビジネスの構造を説明します。
ビジネスモデルは、単純に商品やサービスを消費者に提供して、直接対価を得る方法だけではありません。消費者にはコンテンツを無料で提供し、コンテンツの中に埋め込む広告を出稿する企業から対価を得るといった方法もあります。
新規事業に参加する関係者と、その関係、モノやカネの流れを図示することが有効です。誰に、どのようにアプローチすれば収益を上げられるか、伝えられるように工夫しましょう。
事業計画
事業計画では、新規事業の具体的な実施戦略や実行プランを説明します。
まず、事業を行う市場の規模を明らかにします。市場規模が十分でなければ、事業の成功や将来性が期待できないためです。
そして、新規事業をどのように成長させて利益を得るのか、具体的に示します。柱になるのはマーケティング戦略と収支計画です。
マーケティング戦略で説明するのは、顧客獲得と育成の方法です。どのようなプロモーションを行い、以下の目的を達成するのかを示します。
- 潜在顧客へのアプローチ
- 商品の購入やサービスの利用への誘導
- リピーターへの育成
収支計画では、事業の成長に従って数年分の収支を予想し、説明します。ポイントとなるのは以下の項目です。
- 最初にどれくらいの投資が必要か
- 赤字の出る期間と金額
- 黒字に転換する時期
- 利益の増え方
また、スタートアップ企業などが社外から資金を調達する場合は、投資家へのリターンにも関わる部分です。この新規事業への投資に魅力を感じてもらえる収支になるか確認しましょう。
プロジェクトのゴール
これから行う新規事業で達成したいことを具体的に示します。
どのようなことをゴールに設定するかは、プロジェクトの性質や会社の方針次第です。例えば、以下のようなことがゴールになります。
- 売上高や収益の金額
- 獲得する顧客数や市場シェア
- 事業の確立と持続性の確保
- 新しい商品やサービスの開発
何を持って成功とするのかを定義することで、プロジェクトの方向性が定まります。また、数値で計測可能なものにすることで、進捗状況の把握も可能です。
見込める効果
見込める効果とは、新規事業を行うことで自社にもたらされるメリットを指します。
メリットは会社の事業規模や利益の拡大だけではありません。定量的に測れる項目と、定性的に得られる項目に分けられます。
定量的な効果とは、利益の額、売上高、商品の販売量、市場シェアなどです。比較的数値化が簡単なので、説明しやすい項目でもあります。
定性的な効果とは、ブランド価値や顧客満足度の向上などです。また、新規事業単体ではなく、会社全体への効果も期待できるかもしれません。規模の拡大によりコストを低減できる、社内の設備や人員の合理化ができる、といった内容です。
新規事業の開始について決裁権をもつ経営層に、魅力を感じてもらえるメリットを提示できるよう心がけましょう。ただし、市場調査や財務指標といった客観的なデータとともに提示しなければ、説得力を持ちません。
既存事業との相乗効果の有無
新規事業を行うことで、社内の既存事業との間での相乗効果が生まれるかも大切なポイントです。もちろん経営的な視点では、新規事業が単体として成功するだけでなく、既存事業にも好影響を与えてくれれば魅力が増します。
新規事業で獲得した顧客と既存の顧客を、相互に送客できるかもしれません。すると、既存事業と新規事業両方の成長率が上がるだけでなく、顧客の利便性や満足度が高まる効果もあります。
例えば楽天は、次々と新規事業を立ち上げたり、他社を買収して事業を増やしたりしてきました。そして、社内の事業を、同じ楽天ポイントという特典でつなぐのが特徴です。これにより、既存顧客を新規事業に送客できます。顧客としても、同じ会員情報や決済方法を利用できるため、利便性が高まります。なにより、さらに幅広い分野で楽天ポイントを貯めて使うことが可能となることがメリットです。
また、既存事業で得たノウハウを活かした新規事業ならば、社内の資産を効果的に活用できます。その他にも、既存の設備の稼働率を新規事業で上げられる、従業員に幅広い業務を用意することで離職率を下げられる、なども相乗効果の例です。
想定されるリスク
どのような事業にも、必ずリスクや不安要素はあります。新規事業企画書では、リスクも洗い出して提示することが必要です。
想定されるリスクを提示しておくことで、新規事業企画書の説得力が増します。読んだ人が疑問に思った点、リスクがあると感じた点に、あらかじめ答えを用意しておけるためです。新規事業の計画とリスクを考慮して、成功可能性を推測する手がかりにもなります。
また、想定されるリスクが実際に発生した際の対処方法も説明しておきましょう。事業計画の柔軟性を示すとともに、損失が拡大しないことも納得してもらうためです。
リスクは、自社内、競合他社、市場、周辺環境など、さまざまなところから発生します。国際情勢や法律が変わる可能性もあります。市場、競合、環境について、十分な調査を行いましょう。
競合比較
ほとんどの事業においては、競合が存在します。自社が独自に開発し特許を得た商品やサービスで、まったく新しい市場を生み出した場合であっても、競合が参入してくるものです。そのため、競合の分析と自社との比較は常に必要です。
すでに市場があり、先行している競合がある場合、どのような点で自社が優位に立てるのかを説明します。例えば、商品やサービスが優れているため、価格が安いため、プロモーション方法が異なるため、などです。
もし新しい市場を生み出す場合には、潜在的な競合を想定します。どのような参入者が現れる可能性が高いか、自社がどのような優位性を保てるかを示します。
スケジュール
新規事業を立ち上げるスケジュールを具体的に示します。
説得力を持たせるためには、大まかな設定では不十分です。各段階で必要なタスクを細かく洗い出します。タスクを並べ、重要な項目をマイルストーンに設定して、到達する期日も必要です。
スケジュール作りによって事業計画が現実的になります。また、新規事業開始後には進捗管理にも役立ちます。
新規事業企画書を作成する際のポイント
ここでは新規事業企画書を作成する際のポイントを紹介します。ポイントを押さえて作成することで、新規事業企画書は、さらに効果的に機能するものとなります。
事業の目的を明確にする
なぜ新規事業を立ち上げるのか、その目的を明確に説明しましょう。目的が曖昧だと事業計画の説得力がなくなり、決裁者の承認も得にくくなってしまいます。
新規事業の目的を説明する際のポイントは、理由を外的要因と内的要因に分けて整理することです。
外的要因には、以下のようなものがあります。
- 法律の規制ができた、またはなくなった
- 業界構造に規格化や新技術導入などの変化があった
- 競合他社が値下げ、または値上げをした
- 消費者のニーズが変化した
内的要因は、以下のような自社内のものです。
- 売上が下がった、利益を増やしたい
- 新たに開発した技術を事業化したい
- 新たに入社した従業員の知見を活用したい
- 異業種のノウハウを持つ会社と提携した
自社の経営資源を理解する
新規事業を立ち上げるには、リソースが必要です。まずは自社内の経営資源を調査し、理解しましょう。人員や資金、技術力など、新規事業に必要なものが自社内だけでそろうか確認しなければなりません。
少なくとも、以下の要素を盛り込むことが必要です。
- 初期投資金額
- 新規事業に携わるメンバー
- 商品やサービス開発のための技術やノウハウ
また、すべて社内で用意できる場合でも、複数の部門間での連携が必要なこともあります。その方法やキーパーソンも押さえておきましょう。
もし資源が足りなければ、社外から調達する必要があります。その場合、何を、どのように、どこから工面するのか、計画を説明します。
顧客の声を入れる
新規事業企画書を作成する際は、さまざまな調査を行います。調査から得られたデータを集計し、まとめて、わかりやすく伝えることで、説得力が得られます。市場調査や消費者のニーズについても同様です。
しかし中には、調査結果や情報を加工せずに、そのまま伝えた方が有効なものもあります。その代表例が、顧客の声です。
消費者のニーズを要約データとして示すとともに、いくつかの事例として実際の顧客の声を提示しましょう。読む人にリアリティを感じさせ、調査結果全体の説得力も増します。
事業撤退の基準を定める
新規事業企画書では、収支計画やマイルストーンなどが示されます。新規事業がどのように構築され、成長し、売上や利益を生むかの計画です。
しかし、新規事業にはリスクがつきものです。すべての新規事業が成功するわけではありません。そこで、計画通りに事業を進められなかった場合の撤回基準も、あらかじめ定めておくことが望まれます。
判断基準は具体的に定めるのが基本です。例えば、サービス開始から1年で顧客数が1万人に達していなければ撤退する、5年後に単年黒字化しなければ撤退する、などが基準となります。
撤退基準を設けることで、もし失敗した場合に生じる損失の最大値も計算できます。会社への影響の大きさも考慮して、経営層は新規事業の開始可否や投資規模を判断するのです。
完璧を求めない
新規事業企画書は、一度作って終わりというものではありません。
例えば、追加調査によって情報の精度が高まれば、内容を修正する必要があります。企画を読んだ人からの指摘を受け、対策を追加する項目もあるでしょう。多くの人に読んでもらい、説明していく中で、徐々に完成に近づけていくのです。
また、ビジネスアイデアは、できるだけ早く新規事業企画書の形にまとめるのがおすすめです。事業環境は刻々と変化しています。競合他社が同じアイデアを思いつくかもしれません。タイミングを逃さないためにも、新規事業企画書には完璧さは求めず、まず作成してみましょう。
新規事業を説明するときのコツ
新規事業を立ち上げる前後には、多くの人に事業について説明する必要があります。しかし、用意した企画書やプレゼン用スライドを読み上げるだけでは、相手にうまく伝わりません。ここでは、新規事業を説明するときのコツを紹介します。
スライドに情報を詰め込まない
プレゼンの際に用いるスライドは、文章を読んでもらうためのものではありません。伝えたいことは多くありますが、文字数はできるだけ減らし、情報を詰め込みすぎないようにしましょう。
スライドは、見る人の目を引くキャッチコピーや、要約した短い文で構成することを目指してください。図やグラフを多用し、直感的に理解できるようにする工夫も大切です。あとは、実際にプレゼンの場で、自分の言葉で説明してください。
新規事業は、どのような事業であるかも大切ですが、中心となり推進する人が誰であるかも重要です。プレゼンでは事業の細部まで説明するよりも、概要と熱意を伝えましょう。そして、事業を行う承認を得るか、次の説明の機会を得ることが目的です。
相手の知識に合わせて説明する
プレゼンでは、聞く人に合わせて説明する内容を調整すべきです。聞く人の知識や関心を持つ領域によって、知りたいことは異なるためです。
例えば、経営層や出資者には、事業の展望や収支計画を中心に説明します。新規事業が持つ可能性と、将来的に期待できる利益が最も興味のあることだからです。商品開発や技術に関する専門的な説明には、無関心なことも少なくありません。
しかし、新規事業で一緒に商品やサービスを開発し、運営する人たちは、むしろ専門分野の説明を求めているかもしれません。その場合、活用する技術やオペレーションについて、詳しく説明すべきです。
プレゼン資料はページごとに説明する項目がまとめられています。各ページにかける時間を調整することで、説明にメリハリをつけ、相手に合わせた内容にできます。
プレゼン前に根回しをしておく
新規事業の立ち上げには多くの人や部門が関わります。当然ながら興味の度合いも熱量も、人それぞれ異なります。あまり乗り気でない人に対しては、プレゼンの場だけで説明しても、内容はほとんど伝わらないでしょう。
そこで、事前に説明をする必要があるのです。新規事業について理解してもらい、プロジェクトの進行を了承してもらうことが目的です。そのためには、相手の要望を取り入れて新規事業企画書を修正する必要が生じることもあるでしょう。
また、事前にどうしても賛同を得られない相手もいます。その場合、その人の上司の理解を得ることが有効です。可能な限りプレゼンの前に味方を増やしておきましょう。
新規事業企画書のテンプレート
新規事業企画書には、定まった形式はありません。ただし、新規事業を説明する際に重要になる項目はある程度共通しています。以下のテンプレートをもとに新規事業企画書を作成してみてください。
よくある質問
新規事業企画書の作成や内容に関して、よくある質問をまとめました。
事業計画書は誰が作成する?
新規事業企画書は、基本的に新規事業を立ち上げる人が作成します。ほとんどはビジネスアイデアを発想し、それをもとにして新規事業を行いたい人です。
ただし稀に、会社内に新しい技術や材料があり、それを事業化する役割を担った人が作成する場合もあります。
どちらの場合も、新規事業を運営する際の中心となる人が作成するという点は同じです。
事業計画書の作成費用はいくらですか?
新規事業企画書を個人で作成するのが難しい場合や時間が足りない場合には、作成を代行業者に依頼することも可能です。費用は10万円〜15万円ほどとなっています。
体裁を整えられる、客観的な視点で収支計画などを作成できる、補助金申請などに適した形式にできる、といったメリットがあります。
事業計画書は誰に見せる?
新規事業企画書は、その事業を実行するために承認や協力をしてもらいたい人に見せます。例えば、資金調達が必要ならば出資者や金融機関の融資担当者、社内の承認が必要ならば経営層、一緒に事業を行いたい提携会社や協力会社などです。
まとめ
新規事業企画書の書き方と、その内容について説明しました。
新規事業企画書とは、新しく行いたい事業についてまとめた資料です。新規事業の概要や、利益の出し方、成長計画などを説明します。そして、新規事業を立ち上げるための承認や協力を得たい相手に、納得してもらうためのものです。
また、新規事業企画書を作成することで、他にも多くの効果やメリットがあります。事業計画をタスクまで落とし込んでスケジュール化することで、進捗管理に役立ちます。あらかじめリスクを洗い出し、対策を想定しておくことで柔軟な対応も可能です。
新規事業企画書は完璧なものでなくてもかまいません。ビジネスアイデアを素早く事業化可能な形にするためにも、まず作成することが大切です。紹介した内容やテンプレートを活用し、新規事業企画書の作成に役立ててください。
\開発実績多数!システム開発のプロ集団/