近年では少子高齢化による労働人口の減少により、労働力の確保はつねに深刻な問題です。国際競争力の低下の恐れもあるため、企業は今まで以上に効率的に生産性を向上させる必要があります。
日本政府は「働き方改革」で働きやすい環境を推進してきました。これは労働人口の増加や生産性向上が主な目的です。
今後ますます、国全体での生産性向上が重要になる中、生産性を上げるにはどのような方法があるのでしょうか。生産性向上に成功した企業の例から参考になるヒントを紹介していきます。
さらに、生産性向上を後押しする補助金の存在も、中小企業や個人企業主の方などに向けてわかりやすく解説していきます。
生産性向上とは

生産性とは、企業が投入した経営資源に対する、出した成果の効率をいいます。
「生み出された成果÷投入資源=生産性」という計算式で表せるものです。
投入資源に対し、出された成果の割合が大きいほど生産性が高く、成果の割合が小さいほど生産性が低いことになります。1日に労働力10人で成果が100であれば生産性は10です。生産性向上に取り組んで、同じ労働力で成果が150になれば、生産性は15になり高くなったと言えます。
生産性向上とは、組織の経営資源を最大限に有効活用し、より小さな投資でより大きな成果を生み出すための取り組みです。生産性向上のためには、成果を生み出すために、何らかの施策を実行する必要があります。
生産性を向上させた企業の成功事例を基に得るヒント3つ

企業の中には、働き方改革の推進以前から危機感を感じとり、生産性向上の取り組みを行っていたところも多くあります。そこで、生産性向上のために独自の視点で施策を実行し、成功した事例を、具体的な施策とあわせて見ていきましょう。
事例①ムダを省く製造業務により生産性が向上したトヨタ工場
日本の大手自動車メーカーのトヨタでは、工場での生産性のムダをなくして業務効率を改善させました。
製造業は業務を効率化することが鉄則で、業務効率化が直接的に原価低減の達成につながります。そのためには、付加価値を生まないムダを徹底的に排除する必要がありました。
トヨタ工場では、多様化する消費者ニーズに応えながら収益を上げるために、現場に見られる7つのムダを定義し、排除を実行しています。
その結果、非効率でムダな業務を省くことで生産性向上を成功させました。トヨタの考える7つのムダは、製造工場に限らずオフィスやサービス業でも応用できます。
7つのムダをひとつずつ確認していきましょう。
1.造りすぎのムダ
過剰生産は最も重要なムダで、在庫のムダ・動作のムダ・運搬のムダも発生させる。管理面やタクト設定の緩みから発生して経営に直接影響する。
オフィスでは業務のボリューム以上に会議資料を多く作ることなどがムダである。改善するには、適切なボリュームやタイミングを確認する必要がある。
2.手待ちのムダ
流し作業などは標準時間を構築し、ダラダラした作業がないようにする必要がある。機械の故障で一時的に生産ができない状態や、オート生産中の機械の監視も手待ちのムダと考える。
オフィスでは、個々が複数業務を回すようにし、何もやることがない状態を極力作らないようにする。
3.運搬のムダ
工場内で遠くに運搬することや、必要以上のモノの移動、不要な仮置や積み替えなど。工程バランスの崩れや流れが決まっていない場合に発生する。
オフィスでは使用するコピー機が全員から離れた場所にあると作業効率が悪くなる。情報の流れの悪さや複雑なワークフローもムダになる。レイアウトを変更するなど改善の余地あり。
4.加工のムダ
必要以上の加工・仕上げ作業、本来不要な検査など。標準が決まっていないことで起こる。
ネジを4本締める指示でも、3本で強度が十分な場合は改善する必要がある。
オフィスでは仕事の完成度と関係のない不要な作業を避ける。社内関係者向けの資料作りは極力時間をかけないなど。
5.在庫のムダ
材料・部品・仕掛品・完成品など全てが対象在庫になる。存在する目的がないものはムダな在庫と判断する。在庫の存在で重要な問題を見落とすこともあるので注意する。
故障した場合に在庫でまかなうケースが発生し、さらに多くの在庫を持ちかねない。在庫がなければ、故障を修理するための技術力も身につく。
オフィスで必要のない書類やデータを何年も保存していることが在庫のムダになる。内容に応じて適切な期限を設け、期限を過ぎたら捨てることが必要。
6.動作のムダ
工場内の作業中に起こる不要な動作のこと。意味のない歩行、人や物をさがす、しゃがむ、持ちかえるなどは効率の悪さにつながるのでムダと考える。
オフィスであれば、無駄に席を立つ、業務に必要のない書類を眺めてしまうことなど。
7.不良をつくるムダ
不良品を廃棄・手直し・造り直しはムダと考える。特に廃棄は、産業廃棄物としてコストをかけて廃棄する必要が生じる。不良はあいまいな品質標準など、品質管理の甘さで発生する。
オフィスやサービス業でも、個人のミスやコミュニケーション不足による勘違いなどがムダをつくる可能性が高い。
以上の7つのムダを削減したことで、トヨタは生産性を向上させました。各内容は、どのような業界の会社についても応用できることが多いので参考にしましょう。
事例②分散していた業務を集約し生産性向上に成功したダイニチ工業
新潟のダイニチ工業は、以前はアフターサービスを各営業所が担当するシステムで、問い合わせ対応に多くの時間を費やしていました。そこで、効率化のために、ダイニチ工業では、お客様対応を新潟本社のコールセンターへ集約し、できるだけ電話での対応で完結させたのです。
必要な場合のみ各営業所に業務を割り振るシステムに変更し、各営業所の問い合わせ業務を軽減させることが可能になったということです。結果、残業時間の短縮や休暇が取得しやすい環境が整えられました。
また、生産計画や実績の情報、在庫情報などを集約させる取り組みも行いました。
リアルタイムで情報を入手できるよう、独自にプログラムを構築して生産情報の集約化を実現。生産情報の共有やインターネットでの受発注ができるよう、協力工場約20社を対象にコンピュータ講習を実行しています。
他社も巻き込み、各地に分散していた業務を中央に集約することで、生産性向上につながりました。
事例③労働時間削減により生産性向上に成功した日本航空株式会社

日本航空株式会社は、長時間労働の改善に取り組むことで、生産性向上に成功しました。
以前日本航空株式会社は、デスクワークの社員は深夜残業が習慣化し、多忙を極めていました。2010年の会社破綻をきっかけに、働き方改革を実行しています。
固定電話やデスクトップパソコンを無くし、社員にスマホを配布して自由な場所での業務を可能にしたり、遅い時間のメールや電話を禁止するルールを定めたりしました。
また、働く時間にも柔軟性を持たせています。年休20日取得、月間残業時間4時間を目指して労働時間を削減させた結果、社員の定着率も上がりました。
働き方ニーズの多様化に対応できるよう職場環境を整えた結果、社員満足度が向上したということです。
生産性を向上させるための個人の取り組み

個人のスキルアップは、同じ時間でより多くの利益を生み出せて、組織の生産性向上につながります。個々の能力が高いことは、強いチームを作るための必須条件です。
スキルアップを支援する制度として社内勉強会などの学習機会を定期的に提供するほか、専門資格取得に対して手当を出すなどインセンティブを与えるのも良い方法です。
企業の場合は個人よりも全体での生産性を上げる必要があり、個人の生産性のみを追求すると生産性が落ちてしまう原因になります。チーム全体で最適な行動が取れるようにすることが重要です。
次に生産性向上に向けて個人のスキルアップになる3つの方法を紹介します。
1.タスク管理
メモ帳やノートの管理では、期限を記載してもリマインドはしてくれません。しかし、ツールを使えばリマインドの通知や期限を過ぎた通知を受け取れるので、仕事がスムーズに進められます。必要なタスクを整理しておくことで、仕事のやり残しや遅れなどを防ぐことができます。
2.スキル習得
パソコンスキルの習得や業務に必要な資格などです。特にWord、PowerPoint、Excel関数やVBA習得などのパソコンスキルがあると業務のスピードアップになるでしょう。この他にも、コミュニケーション術や、より高い専門技術の修得など、職場環境で生かせるスキルが身に付けます。
3.モチベーション管理

モチベーションを高めるためには、十分な休暇を取り、会社満足度を高めることが大切です。会社が用意する研修制度や評価制度もやる気を高めるツールになります。福利厚生などを利用し、仕事のオン・オフを切り替えるなど、健康管理にも気を付けましょう。
生産性向上のための補助金とは

国は企業の生産性向上を積極的に支援しています。生産性向上を実行する企業に向けて、補助金や助成金の制度を設けました。
例えば、以下の5つの補助金があります。
- 業務改善助成金
- IT導入補助金
- 人材確保等支援助成金
- 両立支援等助成金
- 人材開発支援助成金
次に、会社が生産性向上のために受け取ることができる2つの助成金について説明します。
生産性向上のためのICTツール導入助成金
東京都では中小企業の生産性向上を促進し、産業の成長を支援する目的で、ICTツールの導入にかかる費用を助成しています。
助成対象のICTツールの内容は以下を参照してください。
- グループウェア
- 時間管理ツール
- タスク管理ツール
- コミュニケーションツール
- ビデオ会議ツール
- 営業支援システム
- 電子契約システム
中小企業の定義は一覧表で確認しましょう。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義
東京都中小企業振興公社による |
| 製造業・建設
業・運輸業等 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
補助金額
補助金額は以下のようになります。
・助成対象期間 交付決定日から原則6か月以内
・助成限度額 300万円(下限30万円)
・助成率 助成対象経費の1/2(小規模企業者は2/3)以内
応募資格・応募方法
・応募資格
助成対象事業者は、以下の①②③④の要件を全て満たす者とします。
①中小企業者又は中小企業団体のうち、法人にあっては東京都内に登記簿上の本店又は支店を有するもの、個人にあっては開業届を提出して営業している者
②東京都内で申請時までに2年(24か月)以上事業を継続している者
③公社総合支援課が実施している「生産性向上のためのIOT、AI導入支援事業における導入前適正化診断」を利用した者、または公社経営戦略課が実施する「ロボット導入・活用支援事業の導入前適正化診断」を利用した者
④過去に、同一テーマ・同一内容でこの助成金を受けていないこと
・応募方法
手順は次のとおりです。
募集要項をダウンロードして詳細を確認し、既定の応募用紙で提出します。
なお、令和3年1月時点で第2期募集は締め切りました。令和3年度の第3期ICTツール導入助成金に関しては4月以降に東京都中小企業振興公社ホームページで確認してください。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
全国中小企業団体中央会が実施している補助金制度です。中小企業・小規模事業者が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。制度変更にも対応し、働き方改革・被用者保険の適用拡大・賃上げ・インボイス導入などが対象です。
補助金額
上限金額・助成額1,000万円で、補助率は経費の1/2、⼩規模事業者は2/3の補助があります。
応募資格・応募方法
・応募資格
応募するためには、以下のように対象経費が定められています。
- 機械・装置、⼯具・器具の購⼊、製作、借⽤に要する経費
- 専⽤ソフトウェア・情報システムの購⼊・構築、借⽤に要する経費
- 改良・修繕⼜は据付けに要する経費
まずは公募に際してのルール・規則を定めた公募要領を確認してください。公募要領をよく読み、申請手続きを行ってください。
・応募方法
申請書はものづくり補助金公式ホームページから入手可能です。申請方法は、インターネットを利用した「電子申請」となります。電子申請システムを利用するためには、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
令和3年の5次応募締め切りは2月19日です。6次応募に関しては現時点で情報がありません。今後の予定はホームページのスケジュールで確認してください。
生産性向上の計画に向けた免除支援策とは

国は生産性向上を行う企業に対して、免除支援という形でのサポートを行っています。先端設備等導入計画で設備投資をする中小企業向けに税制面の特別措置法があります。市区町村の認定を受けることで補助金審査上のメリットが受けられます。
具体的なメリットは2つあり、一つめは税制優遇措置です。計画の中に記載した設備について、固定資産税が取得時から3年間でゼロ~1/2になります。もう一つは、国の補助金施策に対する優先採択などの措置です。具体的にはものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金などが対象です。
「先端設備」の内容については表で確認してください。以下の①②の要件を満たすと工業会証明書が発行されます。
①一定期間内に販売されたモデルであること、最新でなくても良い。
②指標が旧モデルと比較して年平均で1%以上向上している設備であること。
| 設備の種類 | 用途など | 最低価格1台・1基 | 販売開始時期 |
| 機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
| 工具 | 測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
| 器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
| 建物付属設備
2021年3月31日までに購入したもの |
全て | 60万円以上 | 14年以内 |
生産性向上特別措置法
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が生産性向上特別措置法です。北海道から沖縄まで、日本全国1,648の市区町村で実施しています。
免除金額
固定資産税がゼロ~1/2になる設定です。実際には、ほとんどの自治体で固定資産税をゼロにしています。
免除期間
「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、導入された新規取得設備について、最大3年間、固定資産税が免除になります。固定資産税がゼロの場合、中小企業にとってかなりの額が浮くので、余剰金を設備投資などにまわすことが可能です。
応募資格・応募方法
応募資格は「先端設備」を導入して、さらに労働生産性が年率3%以上向上するという計画書を提出した企業が対象です。あらかじめ定められた様式でA4用紙2~3枚程度にまとめる必要があります。
応募の手順は以下の通りです。
1.工業会証明書、認定支援機関確認書を入手
先端設備の定義を満たしている「工業会等証明書」いなければ税制優遇措置を受けることができません。応募要項にも定義が書いてありますが、設備を購入するときに、そのメーカーや商社に、先端設備等導入計画の対象で証明書がでるのかの確認が必要です。
2.申請書の作成
申請書類を一式そろえて市区町村に申請する。
3.認定支援機関確認書の取得
認定取得後に設備を取得し、翌年にその設備について工業会証明書・誓約書とともに税務申告をする。認定後の取得設備だけが税務申告の対象となります。
生産性向上のための指標の計算式とは
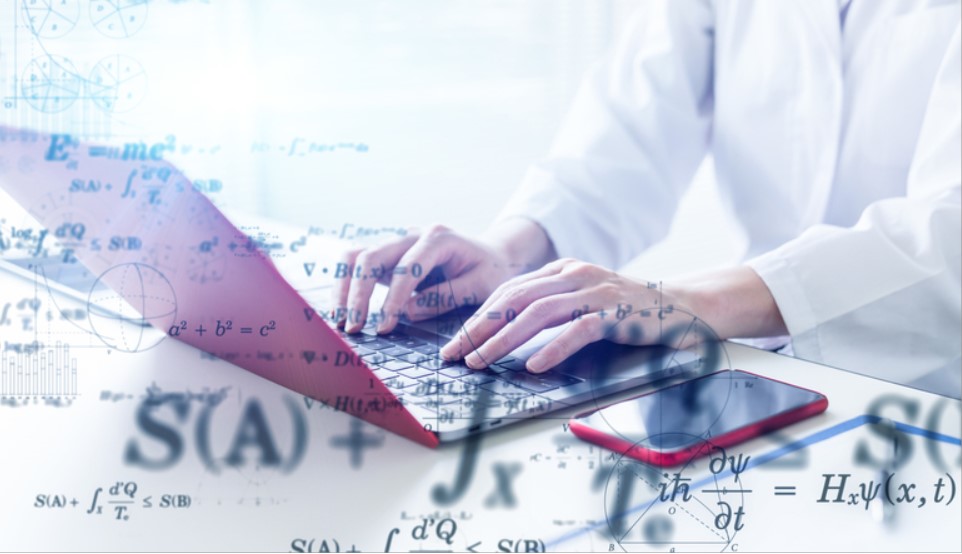
労働生産性とは、「労働者1人あたりが生み出す成果」または「労働者1人が1時間あたりに生み出す成果」を表す指標です。業務効率化のためには欠かせない指標だといえるでしょう。
労働生産性=産出(生産量や付加価値額)÷投入(労働者数または労働者数×労働時間)
「投入」とは、もの造りにかかった原料・人的コスト・設備・土地などを指します。また、「産出」は、投入によってできたモノや生まれた売上を指します。
労働生産性を高めるには、計算式の投入にあたる労働力を抑えながら、効率よく成果を生み出すことが必要です。
なお、労働生産性には「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」の2種類が存在します。
物的労働生産性の定義と計算式
物的労働生産性の計算式配下の通りです。
物的労働生産性=生産量や販売金額÷労働投入量
物的労働生産性は、産出を生産量や販売金額とした場合の労働生産性です。労働者1人あたりが、製品やサービスにどの程度効率的な生産しているかを数値化したものです。生産効率がわかり、品質管理の向上や設備投資の判断に役立ちます。
例として、1,000台のトラックを生産するのに100人の労働者がいた場合、労働者一人あたりの物的労働生産性はトラック10台になります。
付加価値労働生産性の定義と計算式
付加価値労働生産性の計算式配下の通りです。
付加価値労働生産性=付加価値額÷労働投入量
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
付加価値労働生産性とは、産出を付加価値額とした労働生産性のことです。労働者1人あたりがどれくらい付加価値の高い仕事をしているかを数値化します。
成果部分を物の量ではなく、評価した金額による付加価値額により算出します。利益最大化を調べる指標として利用できます。
付加価値労働生産性は、サービス業など異業種間での労働生産性の算出に役立ちます。国際的に生産性を比較する場合は、ほとんどの場合、付加価値労働生産性の計算式が利用されています。
生産性向上のためにはツールの活用も必須

生産性向上のためには、業務の効率化が必要不可欠です。そのための有効な手段がITツールの活用です。たとえば、社内コミュニケーションや情報管理のツールをIT化することなどが代表的な例です。
生産性が低い企業は1人あたりの労働時間が長い傾向があり、残業時間が多い傾向にあります。労務管理や通常の事務にITツールを活用することで労働時間を削減し、業務効率化を推進することができるでしょう。
ITツールを導入するときには、社員が使いこなせて浸透することが重要で、機能が複雑すぎるものは避けるのが賢明です。
次のITツールは導入している企業も多く、代表的なものなので、ぜひ参考にしてください。
| ツールの用途 | ツールの種類 | サービス |
| 労務管理 | プレゼンス管理ツール | FUJITSU Software TIME REATOR
テレワークウオッチ F-Chair+ |
| 勤怠管理ツール | ジョブカン勤怠管理
jinjer勤怠 e-就業ASP |
|
| コミュニケーション | Web会議ツール | Skype for Business
Zoom Google ハングアウト |
| メール・チャットツール | Chatwork
Slack LINE WORKS Microsoft Teams |
|
| データ共有ツール | Google ドライブ
Dropbox Microsoft OneDrive Bo |
|
| 業務管理 | ERP(統合基幹業務システム) | SAP
クラウドERP freee NetSuite |
まとめ

生産性向上は、企業がビジネスを拡大し、維持するために必要なことです。単にITツールや新たなビジネスモデル、フレームワークを導入すれば誰もが成功するわけではありません。それぞれの現状とゴールを見据えて、社内調整や計画、堅実な努力が求められます。
今後は、新型コロナウイルスの感染拡大もあるため、「新しい日常」に合わせた新たな働き方を導入する必要があります。混乱したビジネス環境を生き抜くために、生産性の向上は必要不可欠です。強い組織になるために、生産性向上に向けての対策や方法を、社内でしっかりと検討しましょう。


