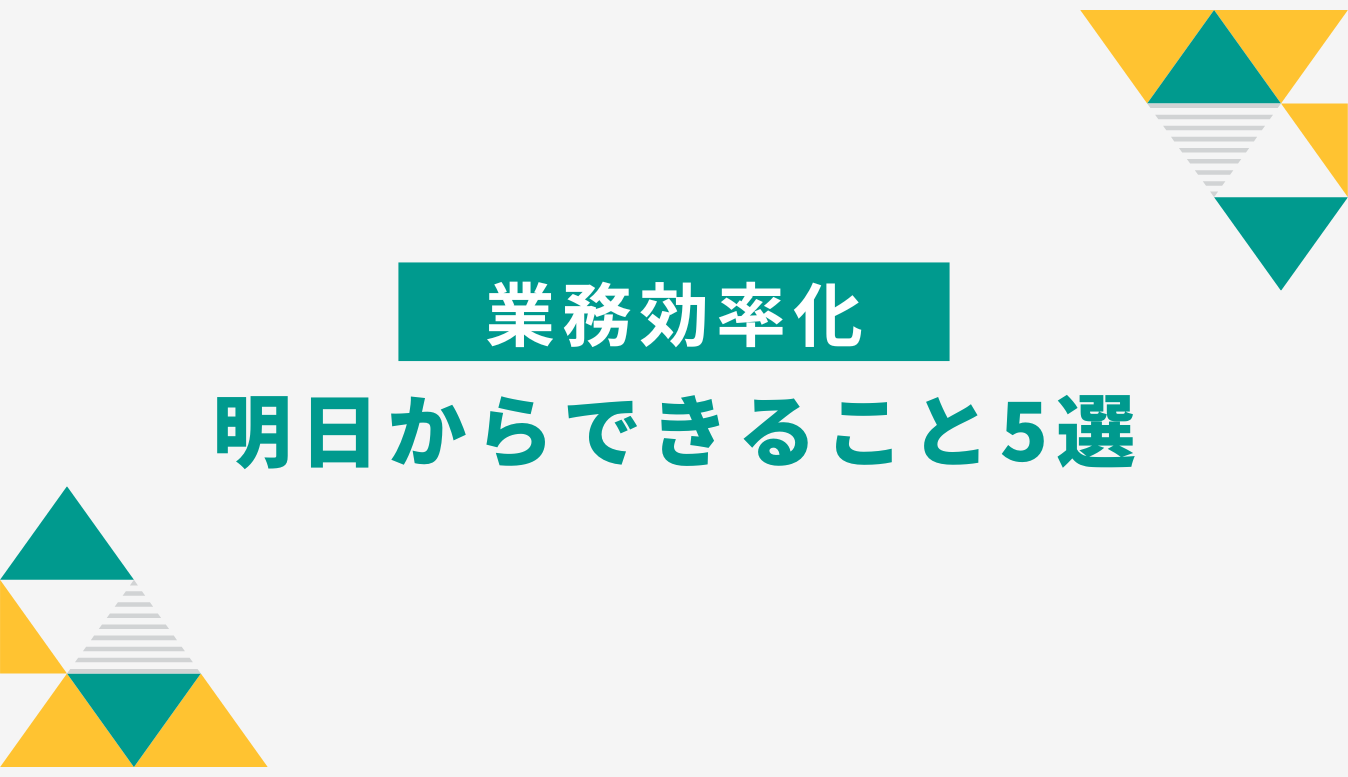はじめに:システム開発 工程を理解すべき理由
システム開発において、各工程(フェーズ)とその役割を正しく理解していることは、プロジェクト成功の鍵です。開発側・発注側双方が工程を共有していれば、認識ズレが減り、品質・納期・コストを統制しやすくなります。
本記事では、「システム開発 工程」というキーワードを軸に、代表的な工程の解説、ウォーターフォール型・アジャイル型の違い、注意点、導入事例などを網羅します。IT初心者・発注担当者・開発者いずれにも有益な内容です。
システム開発 工程(ソフトウェア開発工程)とは
ソフトウェア開発工程(SDLC)という枠組み
ソフトウェア開発工程(Software Development Life Cycle:SDLC)は、構想から設計・開発・運用・保守に至る一連の流れを体系化したものです。
この枠組みを用いることで、各フェーズで成果物や品質チェックを定義し、プロジェクトを段階的に進められます。
一般的なSDLCのフェーズ例としては以下のような流れがあります。
- 企画/構想
- 要件定義
- 外部設計(システム設計)
- 内部設計(詳細設計)
- 実装(コーディング)
- テスト(単体・結合・システム/受入)
- リリース/デプロイ
- 保守・運用
企業・プロジェクトによってフェーズの名称や粒度は若干異なりますが、基本的な流れは広く共通しています。
ウォーターフォール型 vs アジャイル型
伝統的にはウォーターフォール型(各フェーズを順序通りに進める方式)が使われてきましたが、近年は変化に強いアジャイル型手法(例えば Scrum、XP など)が広く採用されています。
| 特長 | ウォーターフォール型 | アジャイル型 |
|---|---|---|
| フェーズ分離 | 各工程を明確に区分け | フェーズを反復的・漸進的に実施 |
| 変更対応力 | 後戻りが難しい | 仕様変更に柔軟対応 |
| ドキュメント重視 | 仕様書・設計書を重視 | 必要最低限なドキュメント+動くソフト重視 |
| リスク管理 | 初期段階でリスク分析 | 定期的レビューでリスク捕捉 |
| 透明性・可視性 | 進捗報告/レビューで管理 | チーム・ステークホルダーとの頻繁な連携 |
アジャイル開発では、短いイテレーション(スプリント)単位で成果を出し、レビュー・修正を繰り返すことで変化に対応しやすくします。Scrum はその代表例の一つです。
各工程の詳細とベストプラクティス
以下では、代表的なフェーズを順に説明し、それぞれで押さえるべきポイントや落とし穴を示します。
企画/構想フェーズ
- 目的・ビジョン整理:システム化の目的、ユーザー価値、ビジネスインパクトを明確化
- 費用対効果・投資判断:要件規模・リスク・投資回収見込みなどを検討
- ステークホルダー調整:関係者との合意形成、利害関係整理
この段階で方向性を固めずに進むと、後工程で仕様変更の嵐に巻き込まれやすくなります。
要件定義フェーズ
- 機能要件・非機能要件の整理:何を「できるようにするか」と、性能・可用性・セキュリティなど
- ユーザー・業務フローのモデリング:画面遷移、ワークフロー、業務ルール
- 優先順位付けとスコープ決定
- プロトタイピング・モックアップ活用
要件定義の精度が低いと、後工程で仕様不整合・手戻りが頻発します。発注者と開発者が認識をすり合わせながら進めることが重要です。
外部設計(システム設計)
- アーキテクチャ設計:全体構造・モジュール分割・技術選定
- インターフェース設計:外部システムとの連携、API仕様など
- 画面設計/データ設計:UI/UX要件、データモデル、ER 図
ここではシステム全体の骨格を固めるため、設計の整合性・拡張性を意識する必要があります。
内部設計(詳細設計)
- モジュール設計・クラス設計:各機能モジュールの責任と構造
- アルゴリズム設計:処理ロジック、条件分岐、性能考慮
- データベース設計の詳細化:SQL、トランザクション、インデックス設計など
- インターフェース仕様:入力・出力、例外処理など
内部設計で曖昧さを残すと、実装時に開発者の解釈差が出やすくなります。ドキュメント整備を怠らないようにします。
実装(コーディング)
- コード実装:仕様に基づいたプログラム開発
- コーディング規約遵守:読みやすさ・保守性の確保
- バージョン管理・コミット粒度設計
実装中は、レビュー工程やペアプログラミング、Lint/静的解析ツール等を併用し、品質を担保します。
テスト工程
テストは複数レベルで行うのが一般的です。
- 単体テスト:モジュール単位の挙動検証
- 結合テスト:モジュール間連携の確認
- システムテスト:システム全体の要件適合確認
- 受入テスト(UAT):発注者またはユーザー環境下で最終確認
テスト設計(テストケース・網羅性・エッジ条件など)を事前準備し、バグ早期発見を目指します。ウォーターフォール型ではテスト設計を設計工程と並行して行うこともあります。
リリース/デプロイメント
- デプロイ計画・手順設計:ステージ環境、本番環境への移行手順
- 移行データ対応:既存データのマイグレーション、バックアップ
- ローンチ後のモニタリング:エラー監視、ログ確認、パフォーマンス監視
リリース時にはリスクを抑えるため、段階リリース(カナリアリリース・ブルーグリーンデプロイなど)を採用する手法もあります。
保守・運用フェーズ
- 障害対応・バグ修正
- 追加要件対応・バージョンアップ
- 運用監視・パフォーマンス改善
- 仕様変更・機能改善対応
システムが稼働した後も、環境変化・要件変更に対応しながら長期運用が可能な状態を維持する必要があります。
システム開発 工程における注意点・落とし穴
工程通り進めても、以下のようなポイントを見落とすと失敗リスクが高まります。
- 段階ごとのレビューと合意形成漏れ → 要件・設計段階でステークホルダー合意が曖昧だと後戻りが発生
- 仕様の過剰固定化/過度な変更 → ウォーターフォール型で仕様を固めすぎると、環境変化に対応しづらい
- ドキュメント整備不足 → 設計書や仕様書が不十分だと、開発者間理解差が拡大
- テスト設計不備 → 網羅性不足、境界ケース漏れ、不十分な自動化
- 環境差異・本番移行失敗 → ステージ/本番環境差異、データ不整合などの落とし穴
- 運用負荷無視 → 運用・保守コストを見込まずリリースする
- コミュニケーション不足 → 発注側・開発側間で認識ギャップが生じやすい
工程を守るだけではなく、各フェーズにおける品質ゲート(チェックポイント)とガバナンスを設けることが重要です。